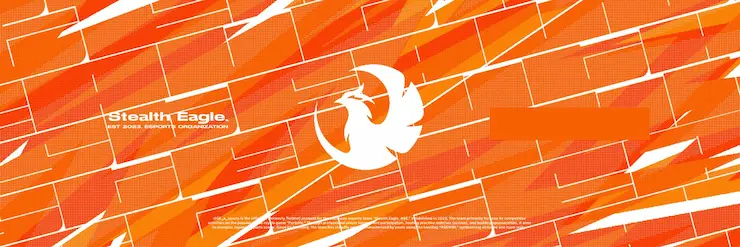PYL Gamingがアドネスゲーミングとして再起。eスポーツプロチーム運営の困難さ
11月1日、アドネス株式会社(本社:東京都新宿区四谷、代表取締役社長:三上功太)は、運営するeスポーツチーム「PYL Gaming(ピーワイエル ゲーミング)」を「アドネスゲーミング」としてリブランディングし、再始動する事を発表。同チームはアドネス株式会社の傘下であったが、今回チーム名を新たにして新体制の元で出発すると銘打っている。

元々あったチームのリブランディングというなかなか無い事態であるが、その背景事情や業界を取り巻く流れについてはかなり複雑な様相を呈している。そこから見えてくるのは、eスポーツチーム運営の困難さだ。
中学生事業者とチームRAPPIT
同チームの源流を紐解けば、合同会社Rappit Entertainmentが運営する日本のプロゲーミングチーム「RAPPIT」がスタート地点となる。当チームは2023年11月より関西を中心に活動を開始。運営元の代表取締役を務める竹内翼氏は当時15歳の中学3年生であり、マーケティング事業などで1000万円の売上を達成した後、2023年7月末にeスポーツチーム「RAPPIT」を設立。同チームには大乱闘スマッシュブラザーズのプレイヤーであるラリックス選手と33ぺらんBOX選手が所属。中学生が立ち上げた企業とeスポーツチームとして当時注目を集めていたとの事である。
しかしこの2名の選手による活動のみでは利益をあげる事が難しく、2025年1月3日、アドネス株式会社に事業譲渡をし、合同会社Rappit Entertainmentもとい株式会社RAPPITとアドネス株式会社の2社での共同運営をスタート。この時チーム名をリブランディングし「PYL Gaming」として再スタートを図っている。事業譲渡先のアドネスは2021年7月に設立された企業であり、次世代型教育事業およびWebマーケティング支援事業を展開。元々Rappit Entertainmentの支援も行っていた企業である。
チームのリブランディングに際し、新たにチームには2名が所属。同じスマッシュブラザーズプレイヤーのルナマド選手、きょう選手を迎えた4人体制で運営を継続していく新たな船出となるはずであった。
リブランディングからの迷走と小規模化
リブランディング後、最初の転機が訪れる事になるのは2025年2月。大乱闘スマッシュブラザーズのプレイヤーであるマイルドなH.O選手が加入して、総勢5名とチーム規模を拡大。活動に弾みがつくかと思われた矢先、33ぺらんBOX選手が同月に脱退。次いで6月にルナマド選手が、7月にきょう選手が脱退。最終的に同チームに残ったのはラリックス選手とマイルドなH.O選手の2名となった。
また2025年5月に「PYL Gaming」の新プロジェクトとして、若手eスポーツプレイヤーを発掘,支援する「PYL Next」というプロジェクトがスタートしている。これは株式会社RAPPITの経営者となっている代表の竹内氏による、大会に出場しようにも金銭的負担が大きいことがネックとなっているプレイヤーに対する支援プログラムであった。こちらはスマッシュブラザーズの大会である「篝火 #13」出場のLeaf選手が対象に選出されており、実際に支援が行われたものと見られる。だが同選手は大会全体で97位と振るわない成績に終わってしまい、更には本プロジェクトの追加情報も無いままとなっている。現状についてはこのプロジェクト自体が凍結されたものと見て良いだろう。
そして今回のリブランディングにおいて、同チームはこれまでの名前ではなくアドネス株式会社のチームとして新たに再出発を図るために名称やユニフォームを変更した可能性は大いに考えられる。「縮小していったPYL Gaming」としての活動に区切りを付けた形となるのだ。
eスポーツ事業の参戦と運営の困難さ
多くの有名プレイヤーやチームが華々しい活躍を見せるeスポーツ事業であるが、実際の所はかなりの茨の道である事もまた事実だ。選手として活動するには必要な機材、大会への遠征費、そしてプロ選手として活動していけるだけの経済的余裕が無くてはならない。専業選手として年間で報酬を得られるプレイヤーの数はごくわずかであり、大体はチームとそれを運営する企業預かりとなる。チームに所属できない場合は個人で活動する他ないが、活動が長期化すればするほどセカンドキャリアとして「一般的な」仕事を目指しづらくなってしまう。
チームを運営・支援するスポンサー側もなかなか手を出しにくいのが現状だ。eスポーツチームに資金提供を行うという事で認知度をあげる事は出来るが、それでもすべてのチームが有名となり、大きなタイトルに挑戦し活躍をしてくれる訳では無い。肝心のチームの戦績が焦げ付いてしまえば、高い宣伝効果が望めなくなってしまうからである。まして広告戦略としては現状Web広告やCMといった物の方が費用対効果が高い現状、余程の戦績や知名度が無ければ企業が応援に回ってくれる可能性は低い。そしてそれは、そのチームを運営する企業にとっても採算性の取れない事業となりかねないのだ。
華々しく見えるeスポーツ業界の中で頑張ろうとする小規模チームは、企業が背後にあるか否かを問わず現在星の数ほどあるだろう。そこから幾つのチームが輝いていけるのか、あるいはすべて淘汰されてしまうのか。願わくは少しでもその受け皿が広くなってくれる事を祈りたいものである。