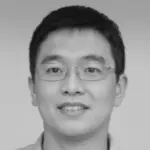マイナビeカレ2026開催決定と全国都道府県対抗eスポーツ選手権の実施 eスポーツが与える社会的影響
株式会社マイナビ(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員:土屋芳明)は11月20日、esportsを楽しむ全ての大学生を対象としたesports選手権『マイナビeカレ 〜esports全国大学選手権 2026〜』の開催を決定した。
また全国都道府県対抗eスポーツ選手権実行委員会は、11月22日(土)に開幕した「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGA」について、23日時点で選抜チームの中から千葉県が総合優勝したことを通知している。
今回の記事ではこの2つのイベントに焦点を当てていく事にしよう。

マイナビeカレとは?
本イベントはマイナビとは名前が付いているものの、株式会社マイナビが提供している就職・求職には直接結びつかないタイプのイベントである。マイナビ曰く、esportsはすでに遊びの域を超えて、多くの大学生の様々な経験や交流、学びなどの貴重な機会を創出するきっかけになりつつあるとの事である。多感な時期である大学生活で力を注ぐ価値ある領域として、esportsを楽しむすべての大学生が頂点を目指したくなるesportsイベントを新設すべく、2023年3月に第1回目となる『マイナビeカレ ~esports全国大学選手権~』が開催されているという。
今回第4回目となる『マイナビeカレ ~esports全国大学選手権 2026~』は、昨年に引き続き、「Apex Legends」と「STREET FIGHTER 6」が競技タイトルとして設定されており、2025年11月20日(木) ~ 2026年1月13日(火)17:00までがエントリー日時となっている。予選大会は2026年2月14日(土)にフレンド部門、2026年2月15日(日)に大学対抗部門が開催され、決勝大会は2026年3月18日(水)にAPEX LEGENDSが、2026年3月19日(木)にSTREET FIGHTER 6の大会が行われる。
フレンド部門については「大学生であれば、どの大学のメンバーと組んでも良い」という部門となっており、逆に大学対抗部門は「同じ大学でメンバーが構成されている必要がある」という縛りが設けられている。メンバーに関しては定員3名となっており、これでチームを結成し大会へ挑むことになる。
先述した様に本イベントはマイナビが提供する各種転職サービスに繋がるものではない。ただし格闘ゲームやチーム戦FPSといった「メンバーに対するマネジメント能力、あるいはチームワーク」「計画的な試合運び」「状況に対応する戦略を考える為の発想と対応力の強さ」など、企業側が見るべき要素は幾つも存在する。こういった要素を売りに、いわゆるeスポーツ業界やアミューズメント産業などに飛び込んでいく人材を発掘できる可能性があるのは本大会の大きな特徴である。
全国都道府県対抗eスポーツ選手権は千葉県が総合優勝
11月23日、全国都道府県対抗eスポーツ選手権実行委員会は、11月22日(土)と23日(日)の2日間にわたって開催した「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGA」(「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ」文化プログラム)について、千葉県が総合優勝したことを通知した。

本大会は通常のeスポーツ系イベントとは大きく毛色が異なるものである。通常のeスポーツプログラムであれば運営元はゲームのパブリッシャーや大手メディア企業、あるいは財団などの様な民間団体である事が主流である。地方自治体のような団体が主催するにしても、決してその規模は大きいものではない。だが本大会はいわゆる「国体」であり、第1回の開催当初から、国民スポーツ大会(国民体育大会/国体)の開催地にて実施されているものだ。そのためゲームやエンターテイメント然とした他のイベントとは異なり、純粋に「スポーツ種目として、指定されたゲーム競技の腕前を競うもの」となっている。
競技種目は「eFootball™」、 「パズドラ」、 「ぷよぷよeスポーツ」の3タイトルが選ばれ、大会初日終了時点の順位は、開催地である滋賀県と、大会3連覇中の東京都が125ポイントで並んでトップに。その後を、120ポイントの千葉県と、110ポイントの熊本県が追いかける展開となっていた。「ぷよぷよeスポーツ」の決勝戦は小学生の部で滋賀県代表が、オープン参加の部で東京都がともに勝利。スコア上でのデッドヒートが続く中、「パズドラ」と「eFootball™」で優勝した千葉県が一気に大量得点で400点を獲得。首位の座を奪い、見事に大会初優勝を果たした形となった。
また「グランツーリスモ7」、「鉄拳8」といったメジャータイトルがエキシビションマッチを飾るなど、eスポーツとして知名度のあるタイトルも取り上げられた。本イベントは後援として内閣府、デジタル庁、スポーツ庁、経済産業省がバックについており、いわゆる企業主導のeスポーツ大会とは違う「公営」でのアピールとeスポーツタイトルの存在感を提示する貴重なイベントとなったと言えるだろう。