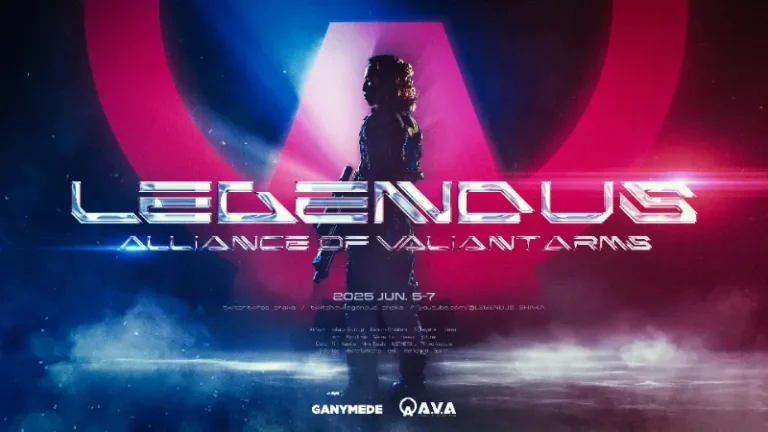eスポーツでは様々な用語が存在し、聞きなれない単語を耳にすることがあります。今回紹介する「スイスドロー」も、聞きなじみの無い方や詳しく知らないという方も多いかもしれません。「スイスドロー」とは、トーナメント戦やリーグ戦のような対戦形式の一種です。eスポーツの大会でも利用され、実際にShadowverseやPokémon UNITEなどの大会がスイスドロー形式で開催されているものもあります。
スイスドローとは一体どんな形式なのか、例を踏まえながら解説していくので、ぜひ参考にしてくださいね。

eスポーツ大会でも利用される「スイスドロー」とは?
トーナメント戦では1度負けると次の試合に参加することはありませんが、スイスドローでは全ての参加者が同じ回数の試合を行います。大会によって細かいルールは異なりますが、無敗のチームが1チームになるまで対戦を行う形式や、最もポイントが高いチームが優勝になる形式などがあります。
こちらの記事もチェック: eスポーツの大会とは?年間スケジュールを紹介
スイスドローの進行手順・計算方法
今回は以下の2つのベーシックな形式で、進行手順を解説していきます。
- 無敗チームが優勝になる形式
- 最終ポイントで優勝が決まる形式
対戦が行われるごとに「実力が拮抗したもの同士が相手になる」のがスイスドロー形式で行われる大会の特徴です。なぜ実力を反映した対戦になっていくのか、進行手順を見ながら詳しく知っていきましょう。
スイスドロー:無敗チームが優勝になる形式
無敗チームが優勝になる形式では、最終的に無敗のチームが1チームになるまで対戦が行われます。
今回の例では、参加チームが8チームの進行について解説をしていきます。
無敗チームが優勝になる形式:スイスドロー1回戦
初戦の組み合わせは、基本的に抽選などのランダムな方法で決められます。抽選によって決まった組み合わせと勝敗は以下のようになりました。
| 勝利チーム | 敗北チーム |
|---|---|
| Aチーム | Eチーム |
| Bチーム | Fチーム |
| Cチーム | Gチーム |
| Dチーム | Hチーム |
無敗チームが優勝になる形式:スイスドロー2回戦
2回戦では、1回戦の勝利チーム同士・1回戦の敗北チーム同士で対戦が行われます。2回戦の組み合わせと勝敗は以下のようになりました。
▼1回戦:勝利チームによる対戦
| 勝利チーム | 敗北チーム | ||
|---|---|---|---|
| チーム名 | 戦績 | チーム名 | 戦績 |
| Aチーム | 2勝0敗 | Bチーム | 1勝1敗 |
| Cチーム | 2勝0敗 | Dチーム | 1勝1敗 |
▼1回戦:敗北チームによる対戦
| 勝利チーム | 敗北チーム | ||
|---|---|---|---|
| チーム名 | 戦績 | チーム名 | 戦績 |
| Eチーム | 1勝1敗 | Fチーム | 0勝2敗 |
| Gチーム | 1勝1敗 | Hチーム | 0勝2敗 |
無敗チームが優勝になる形式:スイスドロー3回戦
3回戦目では、2回戦目までの戦績が同じチーム同士で対戦が行われます。3回戦の組み合わせと勝敗は以下のようになりました。
▼2勝0敗チームによる対戦
| 勝利チーム | 敗北チーム | ||
|---|---|---|---|
| チーム名 | 戦績 | チーム名 | 戦績 |
| Aチーム | 3勝0敗 | Cチーム | 2勝1敗 |
▼1勝1敗チームによる対戦
| 勝利チーム | 敗北チーム | ||
|---|---|---|---|
| チーム名 | 戦績 | チーム名 | 戦績 |
| Bチーム | 2勝1敗 | Dチーム | 1勝2敗 |
| Eチーム | 2勝1敗 | Gチーム | 1勝2敗 |
▼0勝2敗チームによる対戦
| 勝利チーム | 敗北チーム | ||
|---|---|---|---|
| チーム名 | 戦績 | チーム名 | 戦績 |
| Fチーム | 1勝2敗 | Hチーム | 0勝3敗 |
3戦目で無敗のチームが1チームになったため「Aチーム」の優勝です。今回の例では、最終結果は以下のようになりました。
| 最終結果 | チーム名 |
|---|---|
| 優勝 | Aチーム |
| 同率2位 | Bチーム/Cチーム/Eチーム |
| 同率3位 | Dチーム/Fチーム/Gチーム |
| 4位 | Hチーム |
スイスドローでは、このように勝利チーム同士・敗北チーム同士・戦績の同じチーム同士で対戦が行われます。そのため、対戦が進むごとに戦績によって実力が細分化され、より実力の近い相手と対戦が行われるようになっているのです。これはこの後に解説する「最終ポイントで優勝が決まる形式」でも同じことがいえます。
同じ勝率のチームスイスドロー:最終ポイントで優勝が決まる形式
最終ポイントで優勝が決まる形式では、対戦で勝利した方に任意のポイントが付与され、最終的に1番ポイントの多い人が優勝になります。
今回の例では、以下の内容で大会を開催するものとして解説します。
■開催形式
- 全3回戦
- 勝者に2ポイントが付与される
- 参加チームは6チーム
最終ポイントで優勝が決まる形式:スイスドロー1回戦
初戦の組み合わせは、最終ポイントで優勝が決まる形式と同じように抽選などのランダムな方法で決められます。抽選によって決まった組み合わせと勝敗は以下のようになりました。
| 勝利チーム | 敗北チーム | ||
|---|---|---|---|
| チーム名 | 保有ポイント | チーム名 | 保有ポイント |
| Aチーム | 2ポイント | Dチーム | 0ポイント |
| Bチーム | 2ポイント | Eチーム | 0ポイント |
| Cチーム | 2ポイント | Fチーム | 0ポイント |
ルールにのっとり、勝利チームには2ポイントが付与されます。
最終ポイントで優勝が決まる形式:スイスドロー2回戦
2回戦は「得点が同じチーム/ポイントが近いチーム」で試合が組まれます。しかし、今回の大会では参加チームが6チームのため、2ポイントのチームと0ポイントのチームが対戦する試合が1試合できることになります。
2回戦の勝敗はこちらです。
| 勝利チーム | 敗北チーム | ||
|---|---|---|---|
| チーム名 | 保有ポイント | チーム名 | 保有ポイント |
| Aチーム | 4ポイント | Bチーム | 2ポイント |
| Cチーム | 4ポイント | Dチーム | 0ポイント |
| Eチーム | 2ポイント | Fチーム | 0ポイント |
最終ポイントで優勝が決まる形式:スイスドロー3回戦
最終戦である3回戦は、ちょうど同じポイント同士の組み合わせになりました。
3回戦の勝敗はこちらです。
| 勝利チーム | 敗北チーム | ||
|---|---|---|---|
| チーム名 | 保有ポイント | チーム名 | 保有ポイント |
| Aチーム | 6ポイント | Cチーム | 4ポイント |
| Eチーム | 4ポイント | Bチーム | 2ポイント |
| Dチーム | 2ポイント | Fチーム | 0ポイント |
全3回戦の結果により、最終ポイントで優勝チームが決定します。今回の例では、最終結果は以下のようになりました。
| 最終結果 | チーム名 |
|---|---|
| 優勝 | Aチーム |
| 同率2位 | Cチーム/Eチーム |
| 同率3位 | Bチーム/Dチーム |
| 4位 | Fチーム |
3回戦で優勝チームが決まりますが、全チームの順位を決定する場合には、同率2位と同率3位のチームで順位決定戦を行います。
こちらの記事もチェック: スクリムとは?Apex等のスクリム参加方法

スイスドローで大会進行をする際に使えるツール
スイスドローで大会を開催する際、勝敗を管理するのに労力がかかってしまうのではないかと悩んでいる方もいるでしょう。インターネット上では、フリーで利用できる「スイスドロー計算用のツール」を公開している方がいます。
フリーのツールといえど「勝ち点を計算してマッチング」「順位を表示」と便利な機能を備えたツールが多数公開されているので、スイスドローで大会進行にとても役立つはずです。
スイスドローのメリット
スイスドローで大会を開催する場合、以下の3つのメリットがあります。
- 参加者全員が同じ数の試合を行える
- 試合を重ねるごとに実力の近い相手と対戦ができる
- かかる時間が少ない
トーナメント戦では1度試合に負けてしまうとその後の試合に参加することができませんが、スイスドローでは参加者全員が同数の試合を行うため、暇を持て余す選手がいなくなります。また、試合数を重ねるごとに実力の近い相手と対戦をすることができるので、同レベルでの試合を楽しむことができるのです。
全参加者が同数の試合を行うためスイスドロー形式の大会は時間がかかるかと思いますが、実際はトーナメント戦より少し時間がかかる程度。あまり実施時間が長くならないというところもこの形式のメリットです。
スイスドローのデメリット
メリットの多いスイスドロー形式ですが、以下のようなデメリットもあります。
- 形式が複雑なため、参加者が分かりづらい場合がある
- 試合終了後に次の対戦相手が決まるため、大会運営に負担がかかる
トーナメント戦やリーグ戦といって基本的には誰でも知っているという形式ではないため、参加者に進行方法が伝わりづらい場合も。また、対戦結果によって次の相手が決まるため、進行や運営に負担がかかる可能性があります。
まとめ
この記事では「スイスドロー」がどのような形式なのか、例を用いて解説しました。
トーナメント戦やリーグ戦など形式とは異なり少し複雑な進行ではありますが、多くの試合に参加できる・実力の近い選手と対戦できるなど、参加者にメリットの多い形式です。eスポーツでは、予選大会やカジュアル大会などでも利用されているので、参加する大会でこの形式が利用されるという方もいるかもしれません。
ルールや進行方法を理解して、よりeスポーツ大会の参加や視聴を楽しんでいきましょう!