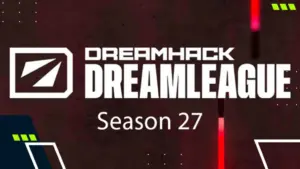GeeSports専用タイトル「Gerogue(ジェローグ)」、京都府知事杯シニア・ジュニアeスポーツ大会の競技タイトルに採用

11月25日、株式会社デジタルハーツホールディングス(本社所在地:東京都新宿区、代表取締役社長 CEO:筑紫 敏矢) が資本参加しているGeeSports万博実行委員会有限責任事業組合(以下、「GeeSports LLP」)は、GeeSports用ゲーム『Gerogue(ジェローグ)』について、2026年1月18日(日)に京都サンガスタジアムにおいて開催される「京都府知事杯シニア・ジュニアeスポーツ大会」の競技ゲームタイトルに採用されたことを通知した。該当タイトルは以前からGeeSports用タイトルとして高齢者のeスポーツ競技参画の為に提供されていたが、今回は門戸を広げて小学生向けのタイトルとしても提供されるとの事だ。
Gerougueと協力性ゲームの相性
高齢者向けeスポーツカテゴリとして設定されているGeeSportsは、シニア世代である“GrandParents”によるゲームプレイで“Exciting”というワクワク感あふれる体験を得られると共に、自信をつけさせて生活にも張りをもたせるという、シニアを中心とした新しい形のeスポーツ分野の事である。ゲームを楽しむシニアの姿が周囲の人々に“Empower”を与え、シニアを中心に世代を超えたコミュニケーションを生み出すことで多世代が交流する事を目的としている。
とはいえ通常のeスポーツの様なタイトルを要件として設定するのではなく、GeeSportsは「シンプルな操作」「声を掛け合う」「誰もが楽しめる」というコンセプトのもと、シニアであってもプレイ出来るシステムであるタイトルが設定されている。それが今回設定されているGerougueだ。
同タイトルは3人一組でプレイする協力型のアクションゲームとなっている。3対3のチームバトル形式で敵の拠点を破壊したほうが勝者となる。操作は非常にシンプルで方向キーと2つのボタンで操作は完結するので、ゲームの操作に慣れないプレイヤーでも遊べる仕組みだ。
このゲームの一番のポイントは「合体」と「必殺技」を打つ際に行う「味方と息を合わせたボタン同時押し」だ。3人のチームメンバーが同じタイミングで2つのボタンを押すと、合体したり、必殺技が出る。現実におけるチームの連携が勝利の鍵となることから、実際に声を掛け合ってプレイするという独特なスタイルが推奨される。一般的な大会におけるチームプレイ系のタイトルであれば、お互いにコミュニケーションを取りつつ最適な動きを模索する「チームでありながら個人プレイに依存する」展開となるが、本タイトルはむしろ「適切な息のあった呼吸」が重視されるため、何よりも「チームとしての結束」が勝利の鍵となる。
京都eスポーツ協議会の決定とその背景
「京都府知事杯シニア・ジュニアeスポーツ大会」の主催者である京都eスポーツ振興協議会では、GeeSportsが掲げる“ゲーム体験を通じたシニアの健康促進”や“世代を超えたコミュニケーションの促進”という取り組みに着目し、同団体が掲げる理念への賛同を表明している。この評価を受け、京都府が支援するニュースポーツ・eスポーツ競技環境整備支援事業の対象事業であり、京都eスポーツ振興事業の一環である「京都府知事杯シニア・ジュニアeスポーツ大会」において、『Gerogue』が競技タイトルとして採用されることが決定したというのである。
同大会自体は1月18日に行われるものであるが、同タイトルは翌週1月25日の「第3回 近畿2府5県eスポーツ協会連合大会2025」でも大会タイトルとして実施され、同日には併せて「eスポーツ就労支援フェス」が併催される。交流イベントの一環としてGerougeという「とっつきやすいタイトル」を掲げると共に、企業関係者と就職希望者のコミュニケーションツールの一環としてゲームを利用したいという考えがあるのだろう。これまではApex Legendsといったタイトルを用いていたが、今回はより競技性が整っており、そのうえでコミュニケーション能力などをチェックしやすいタイトルとしてGerougueが選ばれた可能性は高い。
今回GeeSports主催となる株式会社デジタルハーツホールディングス曰く「小中学生とシニアがゲーム『Gerogue』の対戦を通じて、コミュニケーションを育むことで、GeeSportsが目指す“ゲームを介した新しいコミュニケーションの形”が実現されることを期待しています。」と語っている。いわゆるeスポーツ自体が「没頭してプレイする」というスタイルのゲームが非常に多く見受けられる中で、アナログ的な「協力し合ってプレイする」というジャンルのゲームがどれだけの影響力を発揮できるのか。大会規模そのものは決して大きくないが、地域を含めたコミュニケーションの一環としてタイトルが展開される可能性に大いに期待したいところである。